シフト作成に毎月多くの時間を奪われている管理者の方がほとんどです。
実は、シフト作成が大変になる店には共通点があります。それは「勤務設計」が体系化されていないことです。
誰が作っても同じ品質のシフトが組める状態をつくれば、手間は半分以下にできます。
この記事では、明日から現場で使える「勤務設計の基本3原則」を、店長向けにわかりやすく整理します。
勤務設計がうまくいかない店で起きている問題
毎回“ゼロから作る”属人化
勤務設計が弱い店では、シフト作成が“作る人の頭の中”に依存します。基準がないため、毎回ゼロから考え直すことになり、作成者が変わると品質もばらつきます。
結果として「店長以外は作れない」「新人が作るとミスが多い」といった属人化が発生し、シフト作成そのものが重労働になります。本来、シフトは判断基準さえ整えば誰でも一定レベルで作れる業務です。
属人化を放置すると、負担もトラブルも増え続けます。
配置基準が曖昧で判断に迷う
「この時間帯は何人必要か」「どの作業は誰ができるのか」といった基準が曖昧なままシフトを作ると、毎回判断に迷いが生じます。結果として、直感や経験に頼った“感覚シフト”になり、過不足のある配置が発生します。
忙しい時間帯で人数が足りなかったり、逆に暇な時間に無駄な配置をしてしまったりと、現場の負担もコストも増大します。明確な配置基準がない状態では、誰が作っても最適化は不可能です。
ベテラン依存で無理な穴埋めが発生
勤務設計が弱い店では、難しいポジションを「ベテランが埋める」という運用になりがちです。しかし、ベテランも当然ながら休みが必要であり、負担はどんどん偏っていきます。
その結果、ベテランの不満や離職リスクが高まり、店全体の安定性が失われます。本来、勤務設計は“誰が休んでも店が回る”状態をつくるためのものです。
ベテラン依存は短期的には便利でも、長期的には現場の崩壊につながります。
勤務設計の基本原則①「必要人数を先に決める」
時間帯別のピーク基準を作る
まず決めるべきは「時間帯ごとの必要人数」です。売上や来客数の波は時間帯で大きく変わるため、ピークに合わせた人数基準は勤務設計の土台になります。
しかしよくあるのが、店長だけが“当然の前提”として持っている人数感を、他のスタッフは一切知らないという状態です。「この時間は最低4人必要」という感覚は店長にとって常識でも、現場メンバーからすると聞かされたこともないという場合が意外と多いです。
だからこそ、ピーク人数を明文化して全員に共有しておくことが重要です。基準が文字として存在すると、誰が作っても判断がブレず、属人化を防げます。
曜日別に“最低人数”を設定する
時間帯だけでなく、曜日でも必要人数は変わります。「土日と平日が同じ人数で回るわけがない」のに、多くの店が明確な曜日基準を持っていません。
曜日ごとの売上・客数の差を基に、最低必要人数を設定すれば、シフトの骨格が自動的に決まります。特に飲食店は曜日差が大きいため、ここを押さえるだけで作成時間は大きく減ります。
作業工程別の必要スキルを整理する
必要人数を決めたら、次に「その人数で何の作業をこなすのか」を整理します。
例えば、仕込み・調理・提供・洗浄など、それぞれの工程に必要なスキルは異なります。工程と役割を可視化しておくことで、「人数は足りているのに機能しない」というミスマッチを防げます。
人数基準だけではシフトは最適化できません。人数 × スキルの両方が揃って初めて“回る配置”になります。
勤務設計の基本原則②「役割とレベルを明確化する」
ポジション×レベル表を作る
勤務設計を安定させるうえで欠かせないのが「ポジション×レベル表」です。
調理・仕込み・レジ・洗浄など、店舗には複数の役割が存在しますが、それぞれに必要なスキルレベルは異なります。
役割ごとの難易度や習熟度を整理し、「誰がどのポジションを担当できるのか」を一覧化することで、シフトの組み立てが一気にスムーズになります。属人化を防ぎ、配置ミスも減らせる最も効果の高い仕組みです。
新人〜中堅〜ベテランの“できる・できない”を可視化
シフト作成で最も時間がかかるのは「この人はどこまで任せていいのか」という判断です。
スキルが曖昧なままだと、毎回確認したり迷ったりするため、作成にかかる負担が増えます。新人・中堅・ベテランなどのレベルごとに、具体的な“できる業務・任せられない業務”を可視化しておけば、判断の迷いが一切なくなります。
結果、誰が組んでも同じ配置判断ができ、育成の指標にもなるため一石二鳥です。
複数人で作成しても同じ判断ができる仕組みにする
勤務設計の理想は「誰が作っても同じシフトが作れる状態」です。そのためには、個人の経験や感覚ではなく、明文化された基準に沿って判断できる仕組みが必要です。
ポジション×レベル表と人数基準が揃えば、店長が作っても副店長が作っても、配置の判断にばらつきが出ません。複数人で作成できる体制は、店長の負担を減らすだけでなく、急な欠勤や業務繁忙時にも強い“持続可能な店舗運営”につながります。
勤務設計の基本原則③「テンプレート化して毎回同じ流れで作る」
組む順番(必要人数→役割→配置)を固定化
シフト作成は「順番」を固定すると一気に楽になります。
最初に必要人数を決め、次に役割を割り当て、最後に個別スタッフの配置を行う。この3ステップを毎回同じ流れで行うだけで、迷うポイントが激減します。
逆に、順番がバラバラだと判断が行き来し、作成時間が倍以上に膨らみます。テンプレート化された流れがあれば、作業の流れが安定し、誰が作っても一定の品質を保てるようになります。
属人化しない“チェックリスト型シフト作成”
テンプレートを最大限に活かすには、チェックリスト化が有効です。
「ピーク人数を満たしているか」「各工程に必要なスキルが配置されているか」「新人が孤立していないか」など、毎回確認すべき項目をリストとして固定します。
チェックリストがあると、店長・副店長・リーダーなど、誰が作成しても同じ水準で判断ができます。属人化する余地をなくし、品質を均一化するための最もシンプルで強力な武器です。
毎月の改善点を1つずつ反映させる方法
勤務設計は、一度作れば終わりではありません。毎月の繁忙状況、スタッフの成長度合い、作業の見直しなどに合わせて改善していく必要があります。
ただし、一度に多くを変えると現場が混乱します。最も効果的なのは、「毎月ひとつだけ改善点を反映する」ことです。
例えば“ピーク人数の見直し”“新人の担当範囲の調整”など、小さな改善を積み重ねれば、半年後には全く別レベルの勤務設計になります。
まとめ(明日から変えられる最小アクション)
まずは“必要人数の基準”だけ作る
勤務設計を一気に整えようとすると、必ず挫折します。最初に着手すべきは、最も効果が大きい「必要人数の基準づくり」です。
時間帯別・曜日別に最低人数を決めるだけで、シフト作成の迷いが大幅に減ります。
店長にとっては当たり前の判断基準も、スタッフにとっては共有されていないことが多いため、まずは人数基準を“全員が見える形”にすることが第一歩です。
次に“役割×レベル表”を1枚作る
人数基準が整ったら、次は「役割×レベル表」を作ることです。誰がどの作業を担当できるのか、どこまで任せても良いのかを一枚にまとめるだけで、配置ミスは激減します。
新人・中堅・ベテランのスキル差も明確になり、育成計画も立てやすくなります。人数基準とレベル表がセットになれば、店長以外がシフトを作っても同じ判断ができる“再現性の高い店づくり”が実現します。
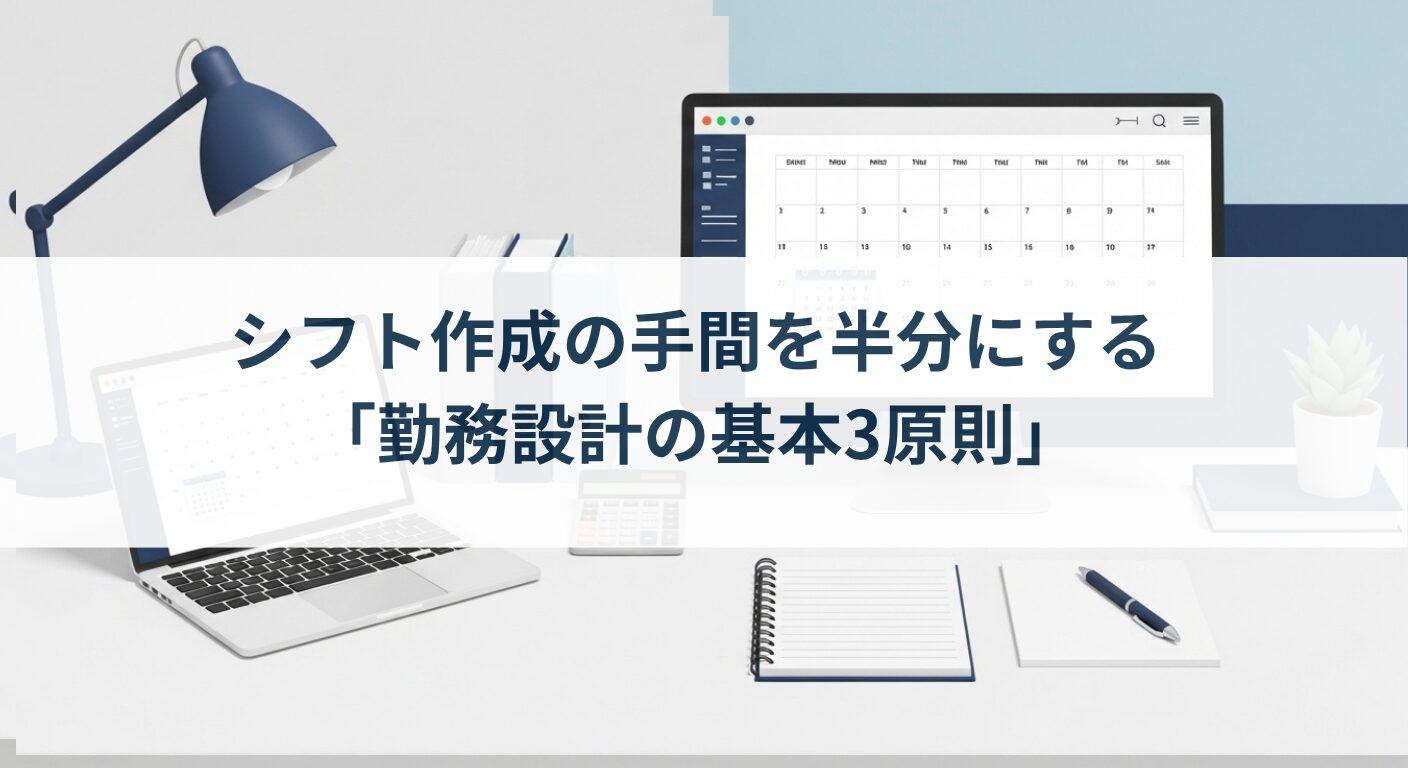

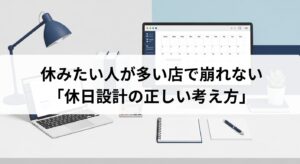
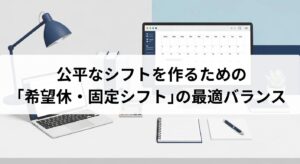
コメント